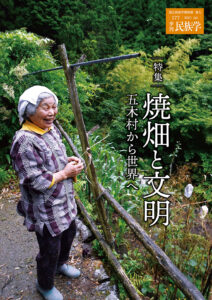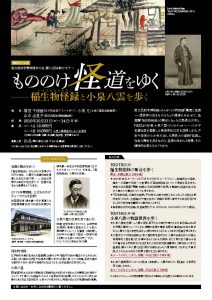【2024/9/18更新】
本催しは満席になりました。
キャンセル待ちにてお申し込みいただいた方には、空席が出次第、9月中を目安にご案内いたします。ご不明な点がございましたら事務局までご連絡ください。
たくさんのお申し込みをありがとうございました。
タイトル
神や精霊の声を聴く――土佐物部の民間信仰、いざなぎ流を訪ねる

内容
「いざなぎ流」は、高知県の北東部、徳島県との県境に位置する香美市物部町に伝わる民間信仰です。山深いこの地では、人びとは「見えない存在」を畏れながら生活を営んできました。いざなぎ流は、そんな物部に伝わる神がみをまつる方法で、生活の変化や急速な過疎化に伴い規模や姿を変えながらも、いまも実施されています。
陰陽道や修験道、密教や神道の要素が入り混じってできたとされるいざなぎ流は、「太夫」とよばれる地域の宗教者によって、その知識が管理・継承されてきました。太夫は人びとの求めに応じて、祭りや祈祷をおこないます。家の神や氏神の祭り、山川の鎮め、医者の少ない時代には、病人祈祷も担っていました。祭礼では、神や精霊をあらわした多種多様な御幣をかざり、神がみの由来や物事の起源を語る祭文を唱えます。太夫は、占いやくじを用いて、神霊に意志を問いかけながら祭礼を進めます。また「スソ(呪詛)」とよばれる呪いの概念が残ることも特徴のひとつです。
本セミナーでは、いざなぎ流に着目し、山間の地で育まれてきた信仰世界と、神や精霊とともに生きる人びとの想像力に迫ります。当日は、月の出を拝む「日月祭」にも参加します。いざなぎ流を支える技術や知識の数々に、信仰の現場でふれることのできる貴重な機会です。ぜひ、ご参加ください。
※詳しい行程はこちらをご参照ください。
講師
梅野 光興
(高知県立歴史民俗資料館学芸員)
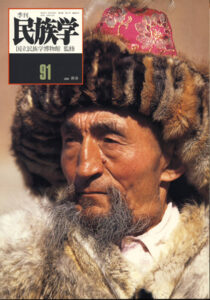
2000年におこなわれた「最後の大祭」ともいわれた祭りを取材。豊富な取材データとともに、いざなぎ流の知識がまとめられています。
日程
2024年10月17日(木)〜18日(金)【2日間】
申込締切
2024年 9月13日(金)
友の会会員(*)は2024年8月2日(金)、それ以外の方は8月9日(金)より受付開始。
*維持会員、正会員、家族会員が対象です。
上記会員以外の方は、維持会員か正会員もしくは体験会員にご登録ください。
募集人数
18名(最少催行人数13名)
※申込先着順
参加費
76,000円
(行程中の移動費、食費、宿泊[相部屋]、見学費を含む)
<<ご参加にあたってのご案内>>
・日月祭では祭りの一部を見学します。18時~22時頃の見学を予定しており、宿への帰着は23時半頃になります(ご希望の方は19時頃に宿にお送りいたします)。
・日月祭は、地域社会に根差した信仰行事です。旅程も「祭りの決まり事」に則って設定しています。通常のセミナーとは異なる時間配分に加え、見やすい場所や休憩場所の確保はお約束できません。他見学者と譲り合ってご参加ください。
お問い合わせ・お申し込みについて
お申し込みは、受付フォームもしくは電話をご利用ください。申込締切日を目安に、参加手続き書類・パンフレットをお送りします。正会員の方は同伴者1 名まで同条件でお申し込みいただけます。
研修企画
公益財団法人千里文化財団 「国立民族学博物館友の会」係
TEL:06-6877-8893 ※受付時間 :平日9:00〜17:00